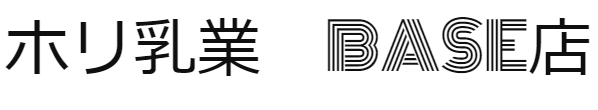ホリ乳業 BASE店 は、現在準備中です。
知られざる酪酸菌のパワーとは😲
酪酸菌概説
日本エンテロビオティックス協会
石原一興
酪酸菌は、糖を発酵して酪酸を生成する菌で、クロストリジウム属という細菌のなかまで、その中のブチリカムという菌種に分類され、学名はクロストリジウム ブチリカムといいます。クロストリジウム属の菌は、酸素がないか少ない環境で増殖し、熱や酸に強い胞子をつくり、棒状あるいは紡錘形をしていて、土壌、植物、動物の消化管に生息、様々な能力を持ち多くの生理作用を示します。酪酸菌は健康にも役立つ有用な菌で病原性は全くありませんが、クロストリジウムの中にはボツリヌス菌やウェルシ菌など病原性を有するものもあります。海外ではクロストリジウムといえばこれら病原菌を思い浮かべ、無害な酪酸菌でさえ整腸剤などとして積極的に利用しているのは日本以外あまりないでしょう(米国などでボツリヌス菌の毒素を美容に利用することはしていますが)。
酪酸菌の整腸作用の発見は、宮入近治によるもので、1933年のことです。その後、酪酸菌は整腸剤として認可されました。まだ抗生物質が発見される前のことですから、食中毒による死亡率も高く感染症対策は大変重要でした。今日の私たちがイメージする整腸効果と当時の整腸効果は大部違います。当時は、腸に入った病原菌の活動を阻害し、消化管から排除し、治癒に役立たせることが主目的でした。今では、有害菌を排除し便通を改善することはもとより、腸の細菌叢を正常に保つことによって体の栄養生理、代謝機能、免疫機能、ホルモン分泌などにさまざまな影響を及ぼし健康を保つことも大きな目的となっています。
酪酸菌には整腸作用のほか、脂質代謝保持機能(血清コレステロール、血清トリグリセライド、体脂肪を正常に保つ機能)、抗アレルギー作用、大腸がんやポリープの予防効果が報告されています。
酪酸菌は消化管では、酸素が少なくなる小腸の下部から大腸で増殖します。それより上部で消化吸収されやすい栄養素はほぼ吸収されていますから、酪酸菌は消化されなかった食物繊維などを栄養源として増殖、主要な代謝物質として酪酸(ほかにプロピオン酸や酢酸)を生成し、炭酸ガスと水素ガスを発生します。酪酸には重要な様々な働きのあることが判ってきています。大腸粘膜細胞の栄養源となり大腸粘膜を正常に保ち大腸粘膜近傍の酸素濃度を低下させ共生菌を維持する、ビフィズス菌の増殖に役立ち腸内細菌叢を正常に保つ、ミネラルの吸収を高める、免疫を制御、肝臓においてコレステロールの合成を抑制する、糖代謝を制御するといった働きのあることが知られていて、酪酸の働きが酪酸菌の有用性の要因の一つと考えられます。
また、酪酸菌は、ビタミンB群、ビタミンKを産生し、コレステロールを変化させ肥満を抑える作用やピロリ菌抑制作用を持つとされるコレステノンをつくるなどの働きもします。
酪酸菌が入っているヨーグルトは、ホリ乳業だけ。